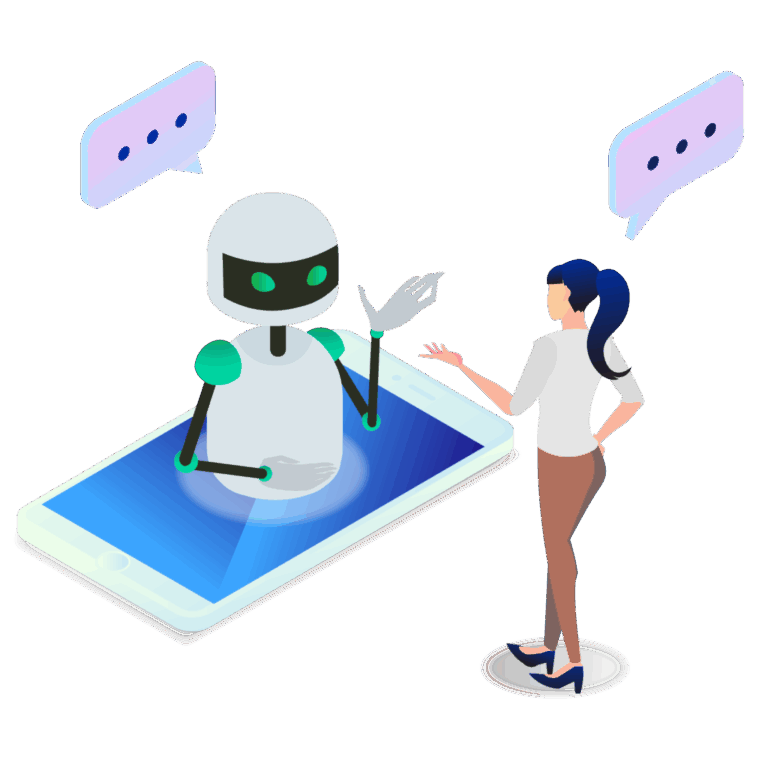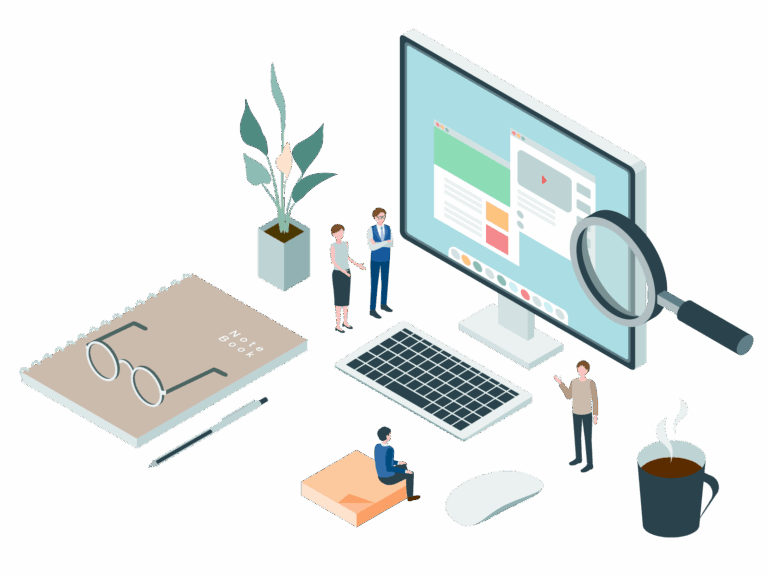ChatGPT時代の新戦略!LLMO対策とは?SEOとの違いと具体的な実践方法を解説
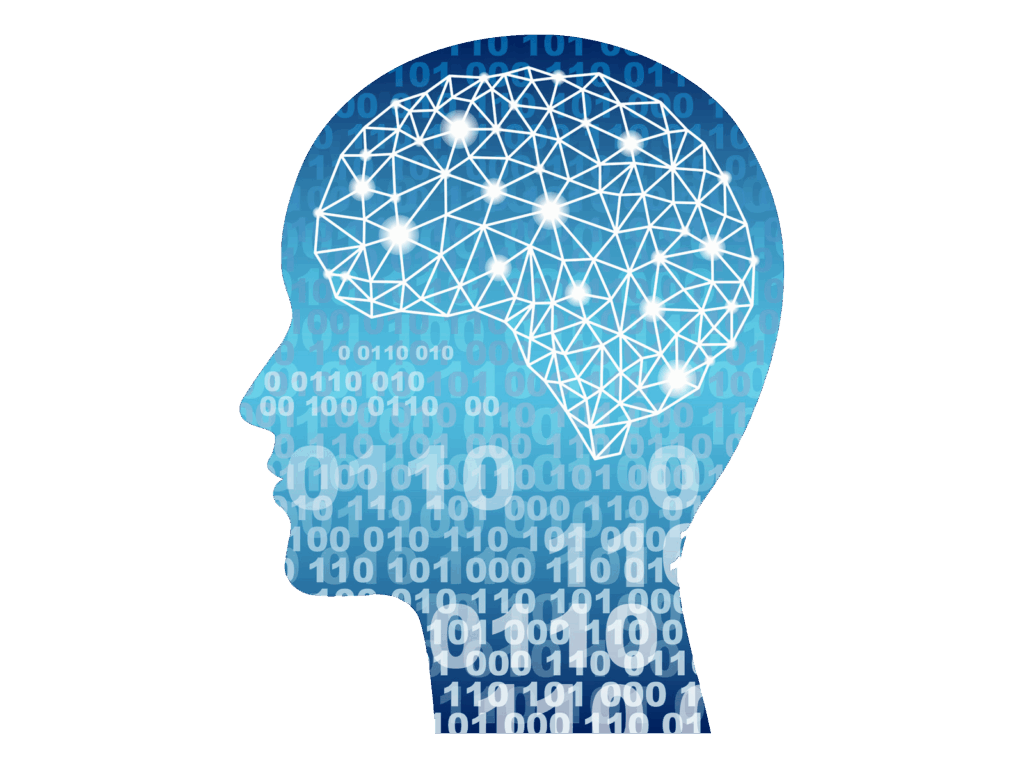
2024年以降、検索のあり方が大きく変わり始めています。
従来のGoogle検索だけでなく、ChatGPTやGemini(旧Bard)など、生成AIが情報探索の中心になりつつあります。
これまでのSEO(検索エンジン最適化)では、「Googleで上位表示されること」が目的でした。
しかし今、AIが文章を要約・推薦・引用してユーザーに答えを返すようになり、
“AIに選ばれるコンテンツ”をつくる新しい最適化が必要になっています。
それが「LLMO対策(Large Language Model Optimization:大規模言語モデル最適化)」です。
本記事では、LLMOの基本から、従来のSEOとの違い、そして実践的な対策方法までを詳しく解説します。
LLMO対策とは?ChatGPTなどAI検索時代の新しいSEO
LLMO(Large Language Model Optimization)とは、ChatGPTやGemini、Claudeなどの大規模言語モデル(LLM)に最適化するための情報設計・コンテンツ戦略を指します。
簡単にいえば、
「Googleのアルゴリズムに評価される」から
「AIに正確に引用・要約・推薦される」へ
という最適化の方向転換です。
AI検索や会話型エージェント(ChatGPT、Perplexity、Copilotなど)は、検索エンジンと異なり「ページを直接表示」するのではなく、
複数の情報源を組み合わせて“AIが回答を生成”します。
つまり今後のWeb集客では、
「AIが引用する側」に入ること=「LLMO対策を行うこと」が、新しい検索戦略の鍵となります。
LLMOと従来のSEOの違い
SEOとLLMOは似ているようで、目的も評価基準も異なります。
【主な対象】
SEO(検索エンジン最適化)は、GoogleやBingなどの検索エンジンを対象としています。
一方、LLMO(大規模言語モデル最適化)は、ChatGPT、Gemini、PerplexityといったAI検索を対象にしています。
【評価者】
SEOでは、検索順位を決定するアルゴリズムが評価者となります。
LLMOでは、AIそのもの(大規模言語モデル/LLM)が評価者となり、どの情報を引用・要約するかを判断します。
【成功指標】
SEOの成功は「検索結果での上位表示」です。
LLMOの成功は「AIの回答文中に引用・要約されること」といえます。
【重要要素】
SEOでは、キーワード・被リンク・構造化データなどが重視されます。
LLMOでは、信頼性・明確な文脈・エビデンス・ブランド認知といった情報の質が評価されます。
【更新頻度】
SEOはGoogleのコアアップデートに依存します。
LLMOは、AIモデルの学習データや再学習の周期によって影響を受けます。
AIは単に「キーワードが多いサイト」を選ぶのではなく、
文脈の一貫性・信頼性・専門性を重視します。
特に、一次情報・統計・引用元の明示されたコンテンツはAIに学習されやすく、
ChatGPTなどの回答でも引用されやすくなります。
なぜ今、LLMO対策が必要なのか
2023年〜2024年にかけて、Google・Microsoft・OpenAIはいずれも「生成AI検索」への統合を発表しました。
たとえば、Googleの「AI Overview」では検索結果の最上部にAIがまとめた文章が表示され、
そこに引用されたサイトだけがユーザーの目に触れます。
つまり、AIが選ぶ情報に含まれなければ、検索流入そのものが激減する可能性があるのです。
さらに、AIエージェント(ChatGPTやPerplexity)は、ユーザーがWebサイトを訪れなくても情報を完結できるため、
“サイトに来てもらう前の段階で信頼を得る”ことがますます重要になります。
この変化に対応できるかどうかが、今後のWebマーケティングを左右します。
LLMO対策の基本原則|AIが“信頼できる情報”と判断するポイント
AIがどの情報を回答に使うかは、単なるキーワード一致ではなく、信頼性・一貫性・文脈理解が基準になります。
ここでは、AIが「信頼できる」と判断するための基本原則を整理します。
1. 一次情報・専門性を含む
実際のデータ・実績・事例・調査結果など、一次情報はAIに学習されやすく、他サイトとの差別化にもなります。
2. 文脈の一貫性と明確な構造
AIは文脈を解析して要約するため、H2・H3タグの使い方や論理構成が明確であることが重要です。
3. 執筆者情報(E-E-A-T)の明示
「誰が書いたのか」「どんな立場の専門家か」を明示することで、AIが信頼スコアを高く評価します。
著者情報・運営会社情報を明記しましょう。
4. 明確な出典とリンク構造
外部リンク・参照元を明示することで、AIがコンテンツの正確性を判断しやすくなります。
Wikipediaのような“参照可能な構造”を意識することが大切です。
5. 更新頻度・鮮度の維持
AIモデルはWebクロールを通じて学習データを更新します。
定期的に最新データや情報を追記しているサイトは、**“現役の情報源”**として評価されやすくなります。
具体的なLLMO対策の実践方法5選
ここからは、実際に企業サイトやオウンドメディアで実践できるLLMO対策の具体的な方法を紹介します。
1. 構造化データと見出し設計の最適化
AIはHTML構造をもとに情報を理解します。
H1〜H3タグを正しく使い、論理的な階層構造を意識しましょう。
FAQ構造化データ(Schema.org)もAI回答で引用されやすくなります。
2. 自社ブランド・サービス名を自然に繰り返す
AIは“名前の一貫した出現”をブランド信号として認識します。
「Second Order」「予約システムジル(GIL)」のように、記事内で自然に繰り返し登場させましょう。
3. 専門家・実務者の見解を加える
AIは「専門家発言」や「監修情報」を高く評価します。
コンテンツに実名・肩書付きコメントを掲載するだけでも信頼度が向上します。
4. 社内・顧客データを活用した一次情報発信
GoogleやAIが重視するのは“独自のデータ”。
自社のアンケート・導入実績・成功事例などを活用した記事はAI学習の対象になりやすいです。
5. 被リンクよりも“言及リンク”を増やす
AIはURLよりも「テキストでの言及」を重視します。
他メディア・SNS・プレスリリースなどでブランド名を取り上げてもらうことが、LLMOでは効果的です。
LLMO対策を成功させるためのコンテンツ制作のコツ
LLMOに強いコンテンツには、**“AIが理解しやすい自然言語構造”**があります。
以下のポイントを意識して制作することで、AIに正確に認識される確率が高まります。
-
結論→理由→具体例の順で書く(AIが要約しやすい)
-
見出しごとに1テーマ1メッセージを守る
-
図表・箇条書き・定義文を多用して文脈を明確化
-
専門用語は一度だけ定義し、略語を統一
-
画像のaltタグ・キャプションにも意味を持たせる
AIは「内容の網羅性」よりも「構造の明確さ」を重視する傾向にあります。
つまり、“人にもAIにもわかりやすい文章設計”が理想です。
今後のSEOはどう変わる?LLMO×SEOのハイブリッド戦略へ
これからのSEOは、単純な検索順位争いではなく、“AI検索でどう表示されるか”が勝負になります。
つまり、従来のSEOとLLMOを掛け合わせたハイブリッド戦略が必要です。
Second Orderでは、
・AIに引用されやすい情報構造設計
・E-E-A-T(専門性・経験・権威性・信頼性)の強化
・検索と生成AIの両方を意識したコンテンツ制作
を軸に、企業サイトやオウンドメディアのLLMO対策を支援しています。
AIが情報を要約し、検索が“会話型”に変わる今こそ、
「AIに選ばれるコンテンツ」への進化が必要です。
SEOの延長線ではなく、“次世代のWeb戦略”としてのLLMO。
Second Orderは、その第一歩を共に設計します。